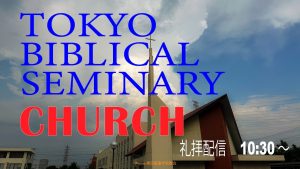説教題:「福音宣教師として」
聖書:テモテへの手紙 第4章1-5節
説教:松島基紀 修養生
賛美:新聖歌266番「罪 咎をゆるされ」1,2,3 新聖歌 434番「語りつげばや」1,2,3
「御言葉を宣べ伝えなさい。時が良くても悪くても、それを続けなさい。」と言う1節の御言葉は非常に有名な言葉です。これは伝道者であるパウロからテモテに宛てて書かれた手紙であると同時に、今日を生きる私たち一人一人にも語られています。5節に書かれているようにクリスチャンであるならばそれは福音宣教者であり、御言葉を宣べ伝える使命が与えられているのです。
なぜ牧師や宣教師だけでなく、すべての人が御言葉を宣べ伝える必要があるのでしょうか。それは宣べ伝える御言葉の性質からくるものなのです。御言葉は神がこの世界に生きるすべての人に向けて語りかける言葉であり、それが私たち一人一人に委ねられているのです。
ではそれはどのような歩みなのでしょうか。それは一言で言うならば御言葉の真理に信頼することです。3、4節にはテモテの周りにいた人々が耳障りのいい言葉を求め、心理から耳を背けていくようになると記されています。これは今も昔も変わらない私たちの姿です。私たちは耳障りのいい言葉、すなわち自分の聞きたい言葉を求めます。しかし御言葉が語るのはそのような私たちの考えや想いを超える神についてなのです。
だからこそ、御言葉を語る時には2節にあるように「忍耐と教えを尽くして、とがめ、戒め、勧める」必要があるときもあるのです。求められている人に思いつく言葉ではなく御言葉の真理がまことの慰めをもたらすことを覚えたいのです。
そして、御言葉を宣べ伝える働きをすることは私たちにとっても大きな恵みとなります。小林和夫先生はこの箇所の説教で、「御言葉というのは、求心的に私たちの心に深く入ってくると同時に、それに釣り合う遠心力をもって人々に伝えられていくときに、より力強く私たちのものになっていくのです。」とおっしゃっていました。これは本当にそうだなと思わされた言葉です。私たちは日々、自分の糧として御言葉を受け取っています。しかしそれだけでは御言葉の恵みの半分しか味わえていないのかもしれません。私たちが聞くことによって御言葉の恵みを感じるなら、その恵みを伝えることでその恵みはより増し加わり、私たちの生活の中で力を発揮するようになるのです。それこそが御言葉に生きる道であり、御言葉を宣べ伝える歩みなのではないでしょうか。