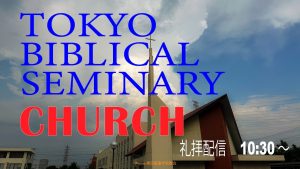説教題:「心を痛まれる神」
聖書:マタイによる福音書 第9章35節-38節
説教:齋藤善樹 師
賛美:新聖歌 第21番「輝く日を仰ぐとき」1,2,3,4、新聖歌 第429番「地の塵に等しかり」1,2,3,4
私達はイエス・キリストを知ることによって神様を知ることができます。イエスの言葉や行動を見て、神はどのような神であるかを知ります。イエスは「憐れみ」の人でいらっしゃいました。イエスは町々村々を巡って、教え、宣べ伝え、癒されたとあります。神はこういう方だと身をもって伝えられたのです。
イエスは私達の具体的な生き方について教えられました。信仰を持って生きるとはどういうことか、人や自分を大事にするとはどういうことか、神を愛するとはどういうことか、時には人間の罪を指摘し、悔い改めることを迫りました。良い教師は生徒のもっている良いものを引き出して育てます。イエスは良い教師でいらっしゃいました。
宣べ伝えるとは、宣伝のことです。宣伝と言えばテレビのCMなどを連想しますが、CMは新しい商品を伝えることが目的です。イエは御国のこと、神の国についてのグッドニュースを伝えました。この世界に愛の神がおられること、人は愛されていること、だから希望をもって生きられること。テレビのCMは作る人が儲けるためですが、イエスの宣伝は儲けなしです。純粋に人のためでありました。
またイエスは語っただけではなく、連れてこられる病人、精神を患った人、悪霊に取りつかれた人々に手を触れて癒されました。大変な労力と時間です。何のためにされたのでしょう?町々や村々で見る人々を深く憐れまれたからです。日本語の「憐れむ」という言葉は何となく「上から目線」のようなニュアンスがありますが、原語のギリシャ語ではそのような意味合いはなく、「内臓」と「痛む」という二つの言葉の合成からできています。日本語でも胸痛むという言葉があります。はらわたが痛むほどの思いをもってひとを見ることです。イエスの前には病人たち、患っている人たちが大勢いました。病人だけではありません。孤独な老人、家庭に問題がある人、夫婦仲、家族関係、飢えた人、悲しみの中にある人がいました。見るからに弱って傷ついている人もいたでしょうが、一見そうではない、元気そうに振舞っている人々もいたことでしょう。けれども、心では泣いていました。明るく笑顔の人も内側では苦しんでおりました。人は自分でさえ気づいていませんが、心は傷ついていることもイエスは知っていらっしゃいました。イエスはそれらの人びとをご覧になって深く心を痛め、それが動機となって、語り、宣べ伝え、癒されたのです。イエスは憐れみの人でした。そこに神がおられました。神はキリストにおいて、人を憐れみ、心を痛められたのです。神は憐みの神、心を痛む神なのです。
愛するとは弱さを持つことです。全能の神に弱さがあり得るのでしょうか?その弱さが現れたのがキリストの生涯であり、イエスの十字架でした。十字架の死にいたるまでイエスの憐れみは変わりませんでした。人々が癒され、生活が立て直され、回復し、幸いになることが神の喜びなのです。
もう一つ忘れてはならないみ言葉があります。収穫が多いが働き手が少ないというイエスの言葉です。目の前で癒され、回復し、本来の生きるべき道に戻る人々が大勢起こされました。イエスはそれを収穫と呼ばれました。世の中の魂のニーズは莫大なのです。しかし、そのニーズにこたえるべく人が少ないのです。イエスは必要な働き手が起こされるように祈りなさいと言われました。もちろん、専門の職業を持つことに限りません。もしかしたら神はあなたの生涯を通して、神の収穫の働き手となることを望んでおられるかもしれません。