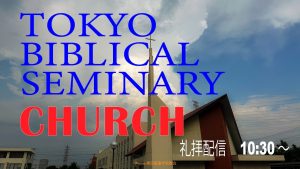説教題:「へりくだりの恵み」
聖書:ルカによる福音書 第14章:7-14節
説教:吉村光 修養生
賛美:新聖歌 第141番 第340番
旧約聖書に記されている、「バベルの塔」は人間たちが自分たちの名をあげるために建てた塔です。人間には、自分を高く見せて、自分の名前を知らせたいという思いがあるのではないでしょうか。祝宴会場で、イエスさまは上席を探す人々に「上席に着かずに、末席に座りなさい」と言われました。この箇所を表面的に読むならば、ただ私たちが祝宴の席で恥をかかない知恵だと読み取れます。しかし、イエスさまは祝いの席で私たちが恥をかかないように、そして上席に案内されるようにとこのような話をされている訳ではありません。
私たちが住んでいる日本では遠慮すること、周りと歩調を合わすことの方が、大抵の場合、上手く生きていくことができます。そういう意味では、イエスさまが言われたように、私たちは末席に座るということに慣れているかもしれません。しかし、いつものように末席に座ることと、「へりくだって」末席に座るということは異なります。私たちが末席に座ったとしても、私たちが本当にへりくだっているのかと問われるならば、心がドキッとするのではないでしょうか。人間は、どんなに謙遜さを持って行動しようとしても、心のどこかで人の上に、上席に座ろうとしてしまう存在です。それでは、一体誰が本当の意味でへりくだることができるのでしょうか。
そこで、私たちは神の御子であるイエスさまが、神の御子という最高の上席におられる方であるのに、地上に来てくださったことを覚えたいと思います。イエスさまは地上に来られ人間と共に生活をしてくださいました。このことに、私たちは本当のへりくだりを見ることができます。イエスさまにとって人間として歩むというへりくだりは全く必要ではありませんでした。神という位にずっと居ても何も問題はありませんでした。けれども、イエスさまはこの地上に来られ、人間にへりくだることに込められた恵みを知らせてくださいました。
マザー・テレサはインドのカルカッタを中心に、貧しい人や病気の人に長い間仕えた人です。彼女はカトリック教徒でしたが、宗教に関係なく貧しい人や病気の人に寄り添いました。彼女はこんな言葉を残しています。「人に親切にすると、隠された動機があるはずだと非難されるかもしれない。それでも親切にしなさい」 マザー・テレサの奉仕を見る人の中には、貧しい人や病気の人に寄り添うことが、彼女自身を偉大な者と見せつけるパフォーマンスではないかと思う人もいました。そして、彼女自身の中にも、貧しい人や病気の人に寄り添う自分自身に鼻が高くなることがあったのではないかと想像するのです。それは他でもない私自身がそう思う時があるからです。人々の苦しみに寄り添うことは一筋縄ではありません。なぜなら、寄り添う人本人が苦しみを担うことがあるからです。だからこそ、自画自賛してみたり、周りの人の反応が気になったり、何か見返りが欲しくなる。つまり、高ぶるのです。しかし、マザー・テレサがそれでも人に親切にするのは、主イエス・キリストが貧しい人や病いの人に寄り添っているだけでなく、人々に仕える時に高ぶってしまう者にも寄り添ってくださっていることを知っていたからだと思うのです。
高ぶりという人間の罪を癒すことのできるのはただ一人、へりくだったお方イエス・キリストです。「へりくだる者は、高められる」。高められるとは、神の御子イエスさまのもとに引き寄せられることです。つまり、真にへりくだられたイエスを知るときに、私たちの高ぶりが明らかにされるだけでなく、私たちはへりくだる者とされるのです。それこそ私たちの高ぶりの癒しであり、イエスさまによって神の前に高められることなのです。 神の愛には上下はありません。貧しい者、病の者だけでなく、高ぶる者にも神の愛は及んでいるのです。へりくだりの恵み。それは、私たちがイエス・キリストを通して知る、私たちへの神の愛なのです。
◆送迎バスの東村山駅の出発時間は10時10分です。